詳細な検査なら人間ドック・がんの早期発見・治療には国が推奨するがん検診を
検診と健診の違いとは?違いを理解し、病気の早期発見につなげよう!
- 健康の要“血管の状態”を把握し、不調を早期発見健康診断の結果はどう見れば良い?健康状態の変化を把握し、病気のタネの見極めを!
- 詳細な検査なら人間ドック・がんの早期発見・治療には国が推奨するがん検診を検診と健診の違いとは?違いを理解し、病気の早期発見につなげよう!
2025.2.28 更新
「健康診断(健診)」は、健康状態を調べるための検査で、前編で紹介した定期健康診断や特定健診があります。このほかに特定の病気を早期発見することを目的にした「検診」や、健診と検診の両方の側面を持つ「人間ドック」もあります。市町村などが行う5大がん検診はがんの死亡率を下げるための検診です。一方、人間ドックは任意に検査項目を選んで詳細な検査を受けられます。それぞれの特徴や検査項目などを知り、上手に活用して、病気の早期発見や将来の疾病予防に役立てましょう。
<ポイントのまとめ>
漠然と「けんこうしんだん」を受けている人も少なくありませんが、いわゆる「けんしん」には、「健診」「検診」「人間ドック」があります。多くの方に馴染み深いのは、会社員が企業で毎年受ける健康診断や40〜75歳の人が自治体で受ける特定健診です。これらは、健康状態を調べるためのものです。これに対して「検診」はがんなどの特定の病気を発見するためのもので、自治体が公共政策として行うものと、個人が任意に行う「人間ドック」があります。
「検診」の中でも科学的根拠をもって、死亡率の低下に寄与するとされているのが自治体の5大がん検診。一方、人間ドックではがんだけでなく様々な疾患に関する検査を受けられますが、必ずしも死亡率低下に関する科学的根拠があるものばかりではありません。検査を受けた後に病気のリスクがあるとの結果が出たとき、どこで治療を受けるのか、そもそも治療の必要があるのかなど、事前に考えておかなければならないこともあります。
もちろん、健康診断を受けることで得られる恩恵は少なくありません。せっかく受けた健診結果を将来の健康に生かすには、健診データを長期保存して“自分の変化を見つめ直す”ことや、検査データに応じた生活習慣の見直し、異変を感じた際の速やかな受診が重要です。人生100年時代のウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)のため、家族全員で健康診断を活用しましょう。
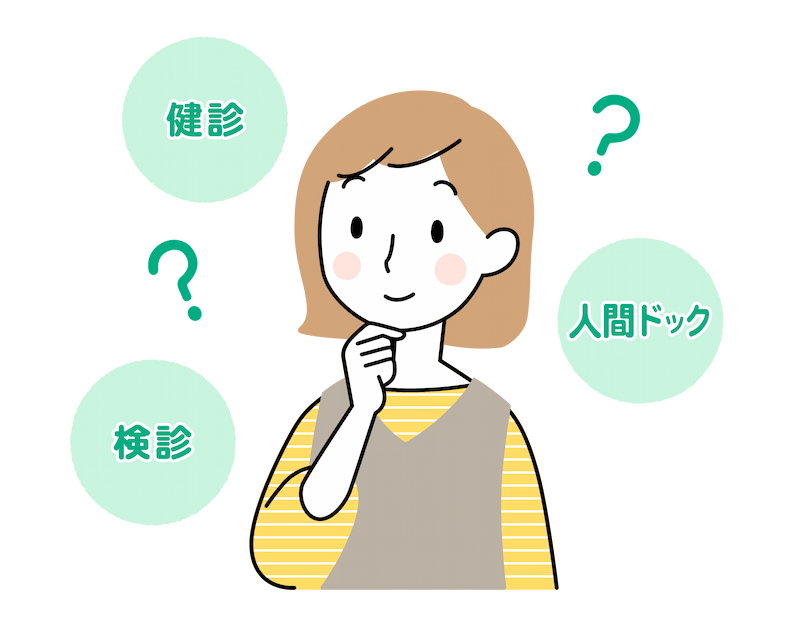
「健診」と「検診」と「人間ドック」はどう違う?
前編で紹介した健康診断(定期健康診断)や特定健康診査(特定健診)は、「健診」といわれるもので、体の健康状態を総合的に確認するプログラムのことです。労働安全衛生法などで実施が義務付けられた会社員が受ける「法定健診(定期健診)」や40〜75歳の人が受ける「特定健康診査(特定健診、いわゆるメタボ健診)」、定期健診に項目を付け加える「付加健診」などがこれにあたります。
付加健診では、定期健診に腹部超音波検査、眼底検査、肺機能検査、詳細な血液検査や尿検査などを追加できますが、単独での検査はできません。協会けんぽが加入者に対して実施している付加健診は、対象年齢が40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳と設定されています。対象者には健診費用の一部負担があります。自治体が行う付加健診の対象年齢や補助金額は市区町村によって異なるので、定期健診や特定健診を受ける際に確認しましょう。
一方、「検診」は、特定の病気を発見することを目的にしています。「検診」はさらに、市町村が実施する「対策型検診(住民検診)」と、医療機関などが任意で行う「任意型検診」に分けられます。対策型検診は「対象集団全体の死亡率を下げること」を目的に公共政策として行われるもので、検診の時期や対象者が決まっています。例えば、後述する5大がん検診は対策型検診で、それぞれの検査は死亡率減少効果が確立している方法で行われ、検診費用は補助されるため安価で受けることができます。
これに対して「任意型検診」は「人間ドック」ともいわれ、「個人の死亡リスクを下げる」のが目的です。「病気の可能性をスクリーニングするという点は健康診断と共通していますが、糖尿病や心血管疾患、脳血管疾患、がんなど、検査する部位や病気にある程度狙いをつけて、詳細な検査を行うケースが多く見られます」と、東京大学名誉教授の北村聖先生は話します。人間ドックは医療機関や健診センターなどが提供するもので、誰でもいつでも任意の検査を受けられます。項目の選択肢が多く、先進的な検査機器を用いた検査が可能だというメリットがありますが、基本的には検査費用は全額自己負担です。
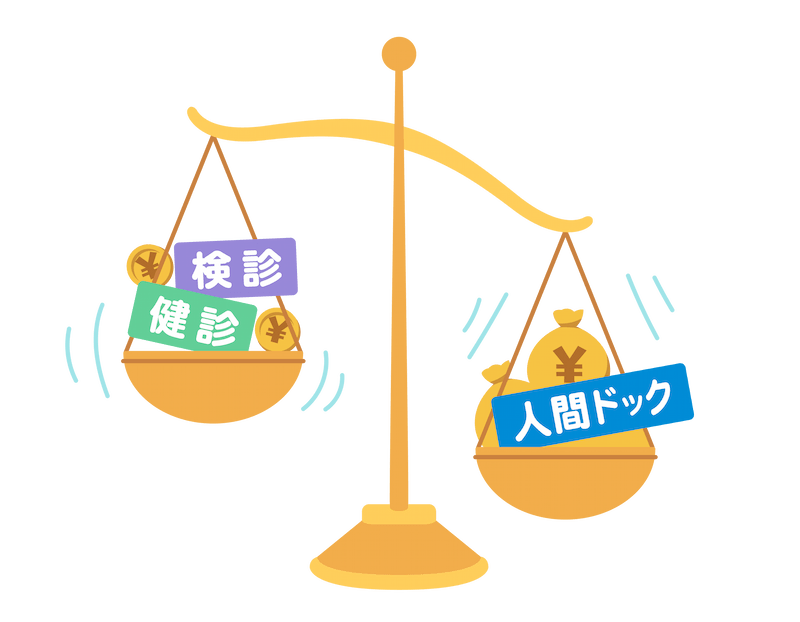
死亡率低下の科学的根拠があり、国が推奨する5つのがん検診
現在、国が推奨しているがん検診は、「胃がん」、「肺がん」、「大腸がん」、「乳がん」、「子宮頸がん」の5つです。日本人の死因の1位を占めるがん※1は、できるだけ早期発見、早期治療をおこなうことで死亡率を低下できるので、対象の年齢になったら定期的に検査を受けるのがおすすめです。
これらの5大がんに対する検診は、がんによる死亡を減らす効果が認められ、なおかつ検診を受ける利益が不利益を上回ることが科学的に認められています。
がん検診を受ける主な利益には次のようなものがあります。
- 標的となるがんによる死亡を防ぐ
- 早期発見により治療が軽度で済む
- がんがなければ「異常なし」と診断されることで安心して生活できる
- 子宮頸がん、大腸がんでは、がんになる前の病変を見つけて治療することでがんを防げる
一方、不利益としては次のようなものがあります。
- 実際にはがんがあるのに精密検査は不要と判定され、がんの治療が遅れる
- 実際にはがんがないのに「がんの疑いあり」と判定され、本来必要のない精密検査を受ける可能性がある
- 治療をしなくても命に関わらないがんが見つかり、本来は不要な治療を受けることになる
- 検診や精密検査での医療行為による合併症として、内視鏡による出血や穿孔(胃や腸などの壁に穴が開くこと)、バリウムの誤嚥や腸閉塞、放射線被ばくなどのリスクがある
| 種類 | 主な検査項目 | 対象年齢 | 受診間隔 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 | 問診および胃部X線検査 | 50歳以上 | 2年に1回 | 検査項目は受診者がどちらか一方を選択 胃部X線検査は当分の間、40歳以上、1年に1回の実施も可 |
| 問診および胃内視鏡検査 | ||||
| 大腸がん検診 | 問診および便潜血検査(免疫法) | 40歳以上 | 1年に1回 | |
| 肺がん検診 | 問診および胸部エックス線検査および喀痰細胞診 | 40歳以上 | 1年に1回 | 喀痰細胞診は50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の人が対象 |
| 乳がん検診 | 問診およびマンモグラフィ(視診・触診の単独実施は推奨しない) | 40歳以上 | 2年に1回 | |
| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診断 | 20歳以上 | 2年に1回 | 30歳以上の検査項目については、自治体がいずれか一方を選択して実施。受診者が検査項目を選択することはできない。 |
| 問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診断 | 30歳以上 | 2年に1回 | ||
| 問診、視診およびHPV検査単独法 (住民検診のみ。厚生労働省が示す要件を満たす自治体に限り実施可能) |
30歳以上 | 5年に1回 |
(注:検査を受ける際は、詳細を自治体に確認してください)
- 1 厚生労働省「令和5(2023)年度人口動態統計月報年計(概数)の概況」による
定期健診や特定健診に、個人で検査を追加するなら
定期健診や特定健診に含まれていない主な検査には、下記のようなものがあります。「これらを人間ドックなどの項目に追加すると、様々な病気の早期発見に役立ちます」と北村先生は指摘します。
- 腹部超音波検査(腹部エコー検査)
- <どんな検査?>
- 超音波を発するプローブ(探触子)を腹部に当てて臓器の画像を撮影する検査で、体への負担は少ない。
- <何がわかる?>
- 腹部の臓器(胆のう、肝臓、膵臓、脾臓、腎臓)のがんや、脂肪肝、胆石、胆のうポリープ、腎結石などの発見に有効。毎年検査することで、生活習慣を起因とする脂肪肝などの変化を観察することもできる。
- 肺(呼吸)機能検査
- <どんな検査?>
- 鼻をクリップでつまみ、スパイロメーター(肺の呼吸機能や肺活量を測定する医療機器)のマウスピースをくわえながら息を吸ったり吐いたりする。
- <何がわかる?>
- 呼吸機能を評価する。
- %肺活量(VC)
- <どんな指標?>
- 性別、年齢、身長から算出された予測肺活量に対し、自分の肺活量が何%か調べる。80%以上が基準値で、79%以下に低下した状態を「拘束性換気障害」という。
- <何がわかる?>
- 代表的な病気に肺線維症や間質性肺炎、じん肺などがある。
- 1秒量(FEV1)
- <どんな指標?>
- 最大に息を吸い込んでから一気に吐き出し、最初の1秒間に何%の息を吐き出せるかを調べる。
- <何がわかる?>
- 気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などを発見する指標として用いられる。1秒率70%以上が正常。
- 努力性肺活量(FVC)
- <どんな指標?>
- 最大限に息を吸ってから一気に吐き出し、最初の1秒間に何%の息を吐き出せるか調べる。1秒率(FEV1)を努力性肺活量(FVC)で割った値を1秒率(FEV1.0%)と呼ぶ。1秒率(FEV1.0%)が70%未満の状態を「閉塞性換気障害」という。
- <何がわかる?>
- 代表的な病気に気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)、気管支炎、肺気腫などがある。
- %肺活量(VC)
- 上部消化管内視鏡検査
- <どんな検査?>
- いわゆる「胃カメラ」で、食道から胃、十二指腸までの上部消化管の内腔を、口または鼻から挿入した内視鏡で観察する。
- <何がわかる?>
- 食道がん、胃がん、逆流性食道炎、胃炎、胃ポリープ、十二指腸潰瘍などを発見できる。
ちなみに、「上部消化管の検査には造影剤のバリウムを飲んでエックス線撮影をする、上部消化管エックス線検査もありますが、内視鏡検査のほうが精度は高いと考えられます」(北村先生)
- 甲状腺機能検査
- <どんな検査?>
- 血液中の3種類のホルモン、甲状腺刺激ホルモン(TSH)・遊離サイロキシン(FT4)・遊離トリヨードサイロニン(TF3)を測定。
- <何がわかる?>
- バセドウ病などの甲状腺機能亢進症、橋本病などの甲状腺機能低下症の発見につながる。
- 肝炎ウイルス検査
- <どんな検査?>
- 採血をして、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスへの感染の有無を調べる。
- <何がわかる?>
- 本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんが移行する患者が多いことから、国が保健所や各自治体が委託する医療機関での無料検査の実施などの取り組みを進めている。
- 前立腺がん(PSA)検査
- <どんな検査?>
- 前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSAの値を見る検査。
- <何がわかる?>
- 一般的な基準値は4.0ng/mLで、490ng/mLを超えると前立腺がんの疑いが高くなる。
北村先生は、「人間ドックなどのがん検診では、血液検査の様々な腫瘍マーカーが用いられることがありますが、この数値はがんがある程度大きくならないと上がらないので、がんを発見するというよりは、治療の経過を確認するのに役立ちます。ただし、前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSAは早い時期から値が上がるので、早期発見にも役立ちます。一般には50歳を目安に検査を受け、近親者に前立腺がんの患者さんがいる場合は40歳ごろから受けるといいでしょう」と説明する。
このほか、健康増進法に基づいて市区町村が実施している「歯周疾患検査」も注目されています。2024年4月から従来の対象年齢である40歳、50歳、60歳、70歳に、これまで対象外だった20歳と30歳が追加されました。「歯周病の原因である歯周病菌は、血管に炎症を起こし動脈硬化を進行させます。脳血管疾患や心血管疾患、糖尿病などのリスクファクターになるため、早期対策が大切です」と北村先生は助言します。
人間ドックなどで受けられる詳細な血液検査とは
また、人間ドックなどでは、健康診断の血液検査項目に加え、様々な血液検査の項目を追加できます。中でも知っておきたい「総たんぱく」「血清アルブミン」「尿酸」「尿素窒素(BUN)」、「アミラーゼ」「CRP(C反応性たんぱく)」についても説明します。
- 総たんぱく
血清中に含まれるたんぱくの総量で、正常値は6.5~8.0(*6.6~8.1)g/dL。
数値が低い場合は栄養障害、ネフローゼ症候群、重症肝障害など、高い場合は多発性骨髄腫、自己免疫性肝炎などが疑われる。 - 血清アルブミン
総たんぱくの中に含まれる数100種類のたんぱく質の中で最も多くを占める。総たんぱくはアルブミンが減ることで低下する。正常値は3.8~5.2(*1.32~2.33)g/dL。ネフローゼ症候群、重症肝障害、栄養不足などで減少する。
- 尿酸(UA)
肉や魚などの動物性たんぱく質に多い核酸の塩基(プリン体)が分解されると出てくる。尿酸値が高い状態が続くと結晶として足の親指の付け根あたりに蓄積し、痛風発作と呼ばれる激しい痛みを引き起こす。正常値は(2~3)~7(*男性3.7~7.8、女性2.6~5.5)mg/dL。7mg/dL以上になると、痛風や無症候性高尿酸血症、腎不全などのリスクが高くなる。
- 尿素窒素(BUN)
特定健診の「詳細な健診の項目」に含まれる「血清クレアチニン」と並び、腎臓の排泄機能の指標となる。正常値は9~21mg/dL。正常値の下限以下では肝不全や多尿、低たんぱく症、高値では腎機能障害や心不全などが考えられる。
- アミラーゼ
唾液腺や膵臓から出る消化酵素で、正常値は60~200(*44~132)IU/L。正常値の上限以上では、急性膵炎や慢性膵炎が多く見られる。
- CRP(C反応性たんぱく)
炎症に伴ってつくられるたんぱく質の一つで、細菌やウイルスの感染や、がんなどによる組織の傷害、免疫反応障害など、様々な原因でからだの中に炎症があると血液中に増加する。CRPだけでは病気の診断はできないが、値に異常が見られた場合はさらに詳しい検査を行う。正常値は0.14~0.3(0.00~0.14)mg/Dl。風邪などの軽い炎症で1.0くらいまで上昇することもある。ちなみに、中年期のCRP値が高いと、高齢期のフレイルのリスクが3〜5倍高まるという研究もある※2。
- は日本臨床検査標準協議会(JCCLS)の「共用基準範囲」(12~13ページ)における正常値の範囲
- 2 J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2019 Feb 15;74(3): 343-349
人間ドックを受ける際には、検査後を想定して事前に相談を
人間ドックでは、上記に挙げた検査項目を追加できるだけでなく、その他の検査項目を追加したもの、MRIやPETなどの最新医療機器を使ったものなどがあります。最近では、「脳ドック」や「呼吸器ドック」「循環器ドック」「物忘れドック」「アンチエイジングドック」「口腔ドック」「メンタルドック」など、各医療機関で様々な人間ドックが提供されています。より詳細に知りたいと思う人も少なくありませんが、受診の際には注意も必要です。
一つ目の注意点は、検査結果が出た後の診療へのアクセスです。「総合病院が実施する人間ドックでは、検査の結果、病気が見つかった場合などに適切な診療科で治療を受けることが可能です。しかし、ほとんどの検診センターやクリニック(診療所)では検査は行いますが、その後の診療は受けられません。人間ドック施設を選ぶ際には、異常が見つかった後にどのような連携システムがあるのかなども調べておくようにしましょう」と北村先生はアドバイスします。
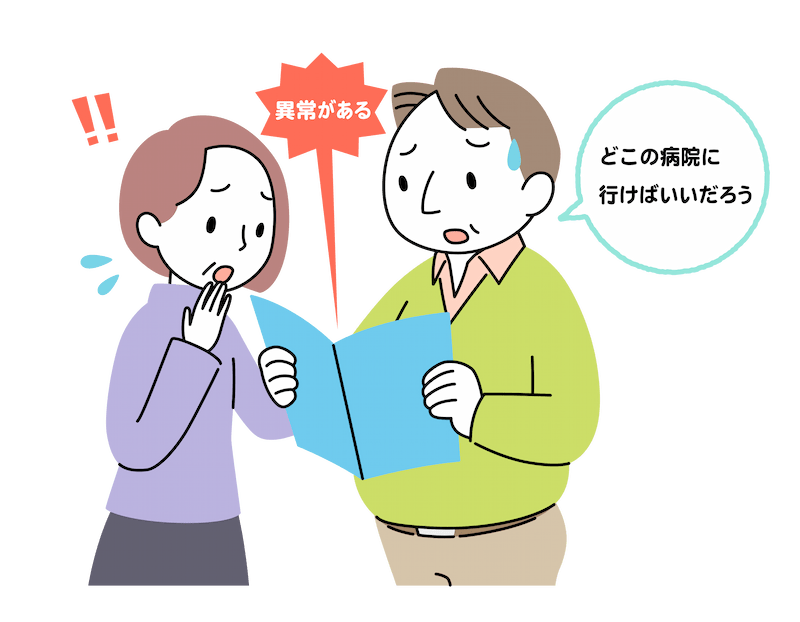
また、もう一つの注意点は、検査結果をどのように受け止めて治療につなげるのかを事前に家族や医療者と相談しておいた方がいいということです。「例えば、脳ドックで未破裂の脳動脈瘤が見つかった場合です。がんとは異なり、未破裂の脳動脈瘤は必ずしも破裂して死につながるわけではありません。それでもリスクを冒して手術をするのか、そもそもその検査を受ける方が良いのかを十分に検討した上で人間ドックを選ぶことが大切です」(北村先生)。
ちなみに、人間ドック施設を選ぶ際には、日本人間ドック学会が定めた「人間ドック検診施設機能評価」の評価基準を満たす「機能評価認定および指定施設一覧」が参考になります。
- 日本人間ドック学会 機能評価認定および指定施設一覧
https://www.hospital.or.jp/pdf/nd_20221205_01.pdf
早めの受診やデータの長期保管、生活習慣改善が大切
健康診断や人間ドックの結果を生かすためには、次の3つを心がけましょう。
1 健診結果のデータを長期的に保管し、経時変化を見る
「若いときの写真を今見ると、当時はこんな服を着ていた、今はシワが増えたなど、変化が一目でわかります。健診結果のデータもそれとよく似ていて、そのときにどんな食生活をし、どのくらい体を動かし、それが体の中でどう処理されたかということが一目瞭然なのです。変化を見ることが大切なので、できれば自分の記録として保管していきましょう」と野口先生。
企業における健診結果の保管期間は労働基準法で5年間と定められています。「今後は5年分の健診結果をグラフ化したり、どのような変化があったかレポートしたりしてくれるシステムの構築が期待されますが、まずは自分自身で10年、20年とデータ管理し、変化を観察していくのがよいでしょう」(北村先生)
2 体の状態や生活習慣を見つめ、改善策を考えるクセをつけて行動を変える
「例えば、減量を目指して1日1万歩程度歩いているのに、なぜか体重が増えるという人がいます。スマートウォッチなどの活動量計で調べてみると、長い距離を歩いているわりには活動量が少ない。その原因は、ゆっくりたらたら歩いていている、階段昇降など筋肉に負担をかける活動がないことにあったりします」(野口先生)
歩幅を大きくして早足で歩く、駅から自宅までの道をいつもより1分でも速く歩くなど、意識と行動を少し変えるだけで、体は良い状態に変わっていくといいます。「ジムなどに通わなくても、家の中で5分や10分単位でこまめに体を動かし、トータルで60分くらいになれば十分な運動になります。掃除機をかける、浴室の掃除をするなど、日常生活の中で体を動かす機会は意外に多いものです」(野口先生)
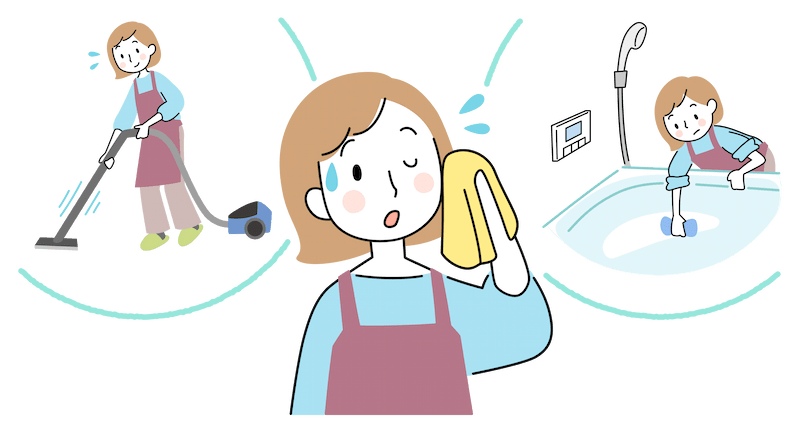
また、食事については、自分ではたくさん食べていないつもりでも、意外にカロリーを多く摂取していることもあります。それを“見える化”するため、朝から夜まで口に入れた食べ物や飲み物をひと通り書き出してみるのもおすすめです。「その際には、キャンディーや清涼飲料水など、砂糖が使われている食品も忘れずにどのくらい摂っているのか数値化することが大切です。減らすべきものが把握しやすくなります。自分に必要な方法を考えて行動を変えていけば、体は必ず変わります。次の健診結果にもその成果が表れるはずです」と野口先生は指摘します。
3 健診結果にかかわらず、自覚症状に気づいたら速やかに医療機関を受診する
「がんの中には、血液のがんである白血病のように急速に進行するものもあります。ある年の健診や人間ドックでは異常がなくても、翌年に検査を受けるまでの間にがんやそのほかの病気を発症する可能性もあります」と北村先生。
病気の早期発見・早期治療のためには、健診や検診だけでなく、「何らかの自覚症状に気づいたら、すぐに医療機関を受診することも重要です」と北村先生はアドバイスします。
北村先生は、「健診は、自分の体の状態を確認し、より健康になり、幸せになるために受けるものです。健診結果を生活習慣改善に生かし、ウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)につなげていきましょう」と助言します。
専門家プロフィール(あいうえお順)
- 北村聖先生
- 東京大学名誉教授。地域医療振興協会顧問。医学博士。東京大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院検査部助教、同大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター教授などを経て現職。専門は臨床病態検査医学、臨床判断学、医学教育。
- 野口緑先生
- 大阪大学大学院医学研究科 公衆衛生学 特任准教授。保健師、医学博士。1986年、兵庫県尼崎市役所入庁。2000年から総務局職員部係長としてメタボに着目した独自の保健指導で実績を上げ、「スーパー保健師」として注目される。2013年、大阪大学大学院招聘准教授。2020年、尼崎市役所を退職し、現在に至る。
- 健康の要“血管の状態”を把握し、不調を早期発見健康診断の結果はどう見れば良い?健康状態の変化を把握し、病気のタネの見極めを!
- 詳細な検査なら人間ドック・がんの早期発見・治療には国が推奨するがん検診を検診と健診の違いとは?違いを理解し、病気の早期発見につなげよう!
