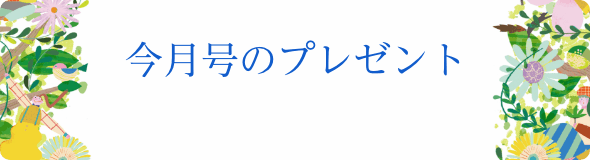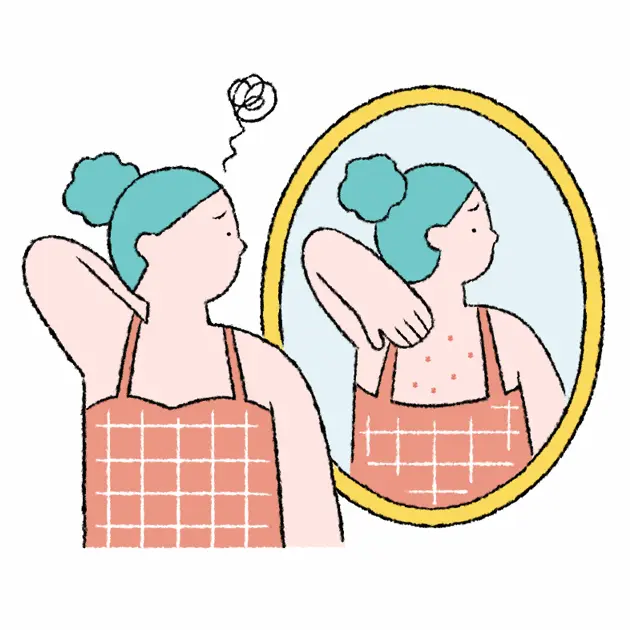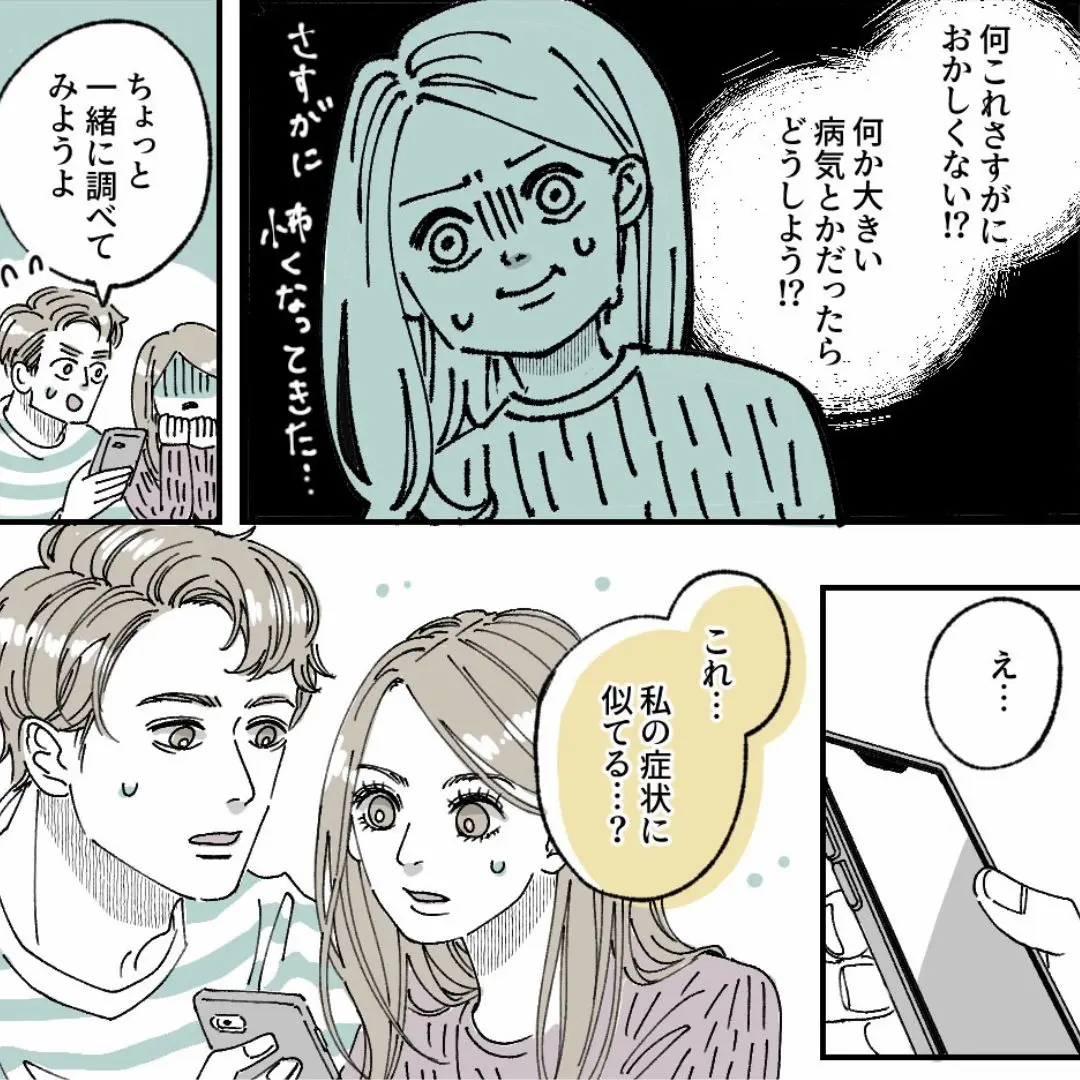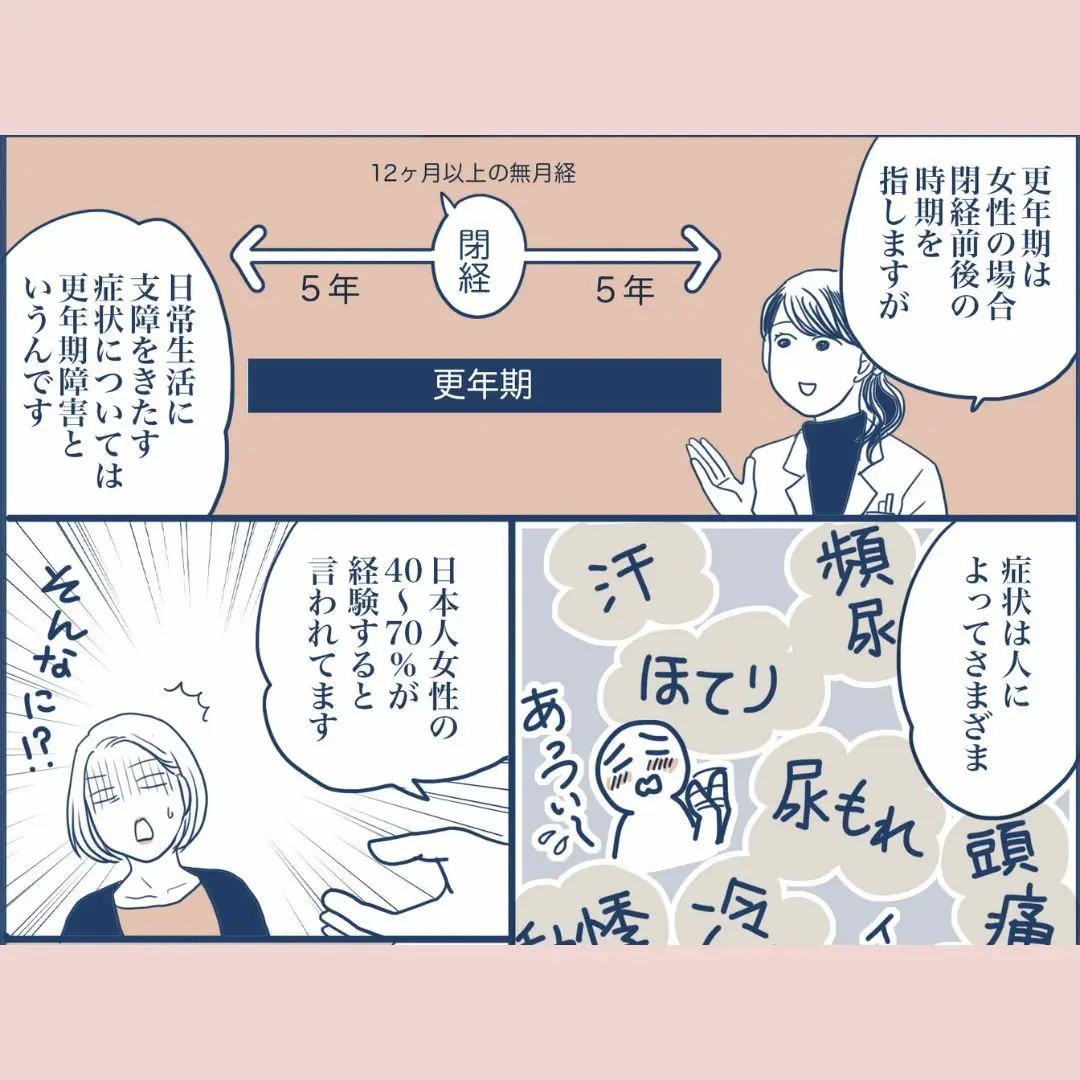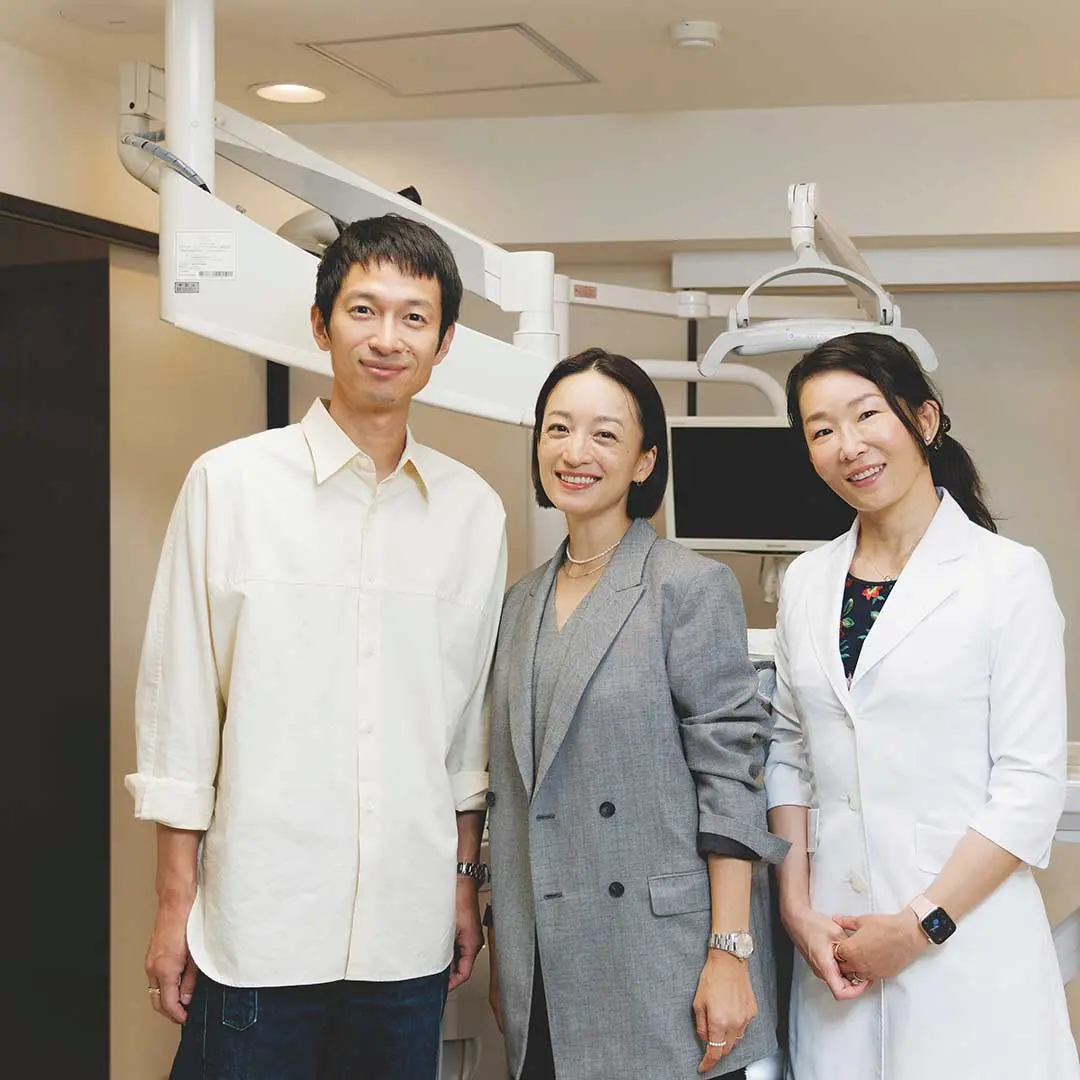「学びの輪」をつなぐ人たち
「健康美塾」では、専門家の先生が
また、さまざまなセルフケアメイトが、
健やかに日々を過ごすための
今月号のプレゼント
![2025年7月のプレゼント「Regain免疫ケア青汁[機能性表示食品]」の画像](/kenko-bijuku/assets/2507_present_20wRK.png)
今月号のプレゼント
Regain免疫ケア青汁
[機能性表示食品]
7月31日(木)17:00まで
Mail Magazine
編集部によるメールマガジン。プレゼントの情報や、毎月更新されるコンテンツなどをお届けしています。
※ドメイン指定受信を設定している場合、「@daiichisankyo.com」の受信を許可してください。
SNSでは、健康美塾で発信したセルフケアにまつわるさまざまな記事の情報を、定期的に投稿しています。SNS限定キャンペーンも実施していますので、お見逃しなく。