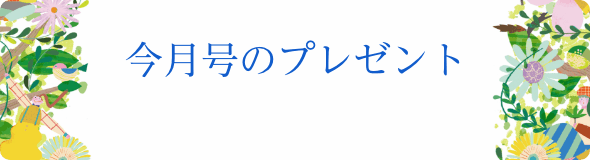隠れ我慢はやめよう!女性のウェルビーイング向上のために大切なこと「ウェルビーイングを考える」【後編】

2025年01月31日
近年耳にする機会が増えてきた「Well-Being(ウェルビーイング)」について、前編では具体的にウェルビーイングとはどういったことなのかを中心に、日本女性ウェルビーイング学会代表を務める笹尾敬子さんにお伺いしました。後編となる今回は、女性総合職第1号として日本テレビに入社した笹尾さんが当時大変だったこと、そして隠れ我慢を続けることの影響についてお聞きしました。
<対談メンバー>
・日本女性ウェルビーイング学会代表:笹尾敬子さん
・第一三共ヘルスケア 広報部 デジタルコミュニケーショングループ長:砂川知子さん
隠れ我慢をしていると、下の世代に影響も
――笹尾さんは女性総合職第1号として日本テレビに入社されましたが、基本的に女性は家を守る存在、働く女性であっても、職場では男性のサポートをする存在という考えが強く、大変なことも多かったのではないでしょうか。
笹尾:私が入社したのは、男女雇用機会均等法が施行される前の1981年。施行に先駆けて、日本テレビが女性総合職の採用に踏み切った年でした。もともと報道の仕事がしたくて、入社後は希望通りに配属されたのですが、社員として若い女性が入ってくるのは報道局にとって初めてのこと。100人はいる大部屋に女性は一人で、朝出社するとその場にいる男性社員が一斉にこちらを振り向いたり、女性が電話に出るだけで、間違い電話だと思われガチャンと切られることも。マスコミ初の警視庁詰め記者に抜擢された時には、スポーツ紙に「紅一点桜田門をくぐる」という大見出しで取り上げられ、その大時代的な取り上げられ方に自分が一番びっくりしましたね。
その後、結婚して娘を出産しましたが、当時は育休という制度が整備される前。3か月の産休だけは認められていましたが、まだまだ女性が社会で働くには厳しい世の中でした。そうやって私自身が大変な思いをしてきたからこそ、後輩の女性のみなさんにはそんな思いをしてほしくないと思っています。昔に比べれば、今の時代はいい方向に変わってきているとは思いますが、まだまだ私たち女性自身がどこか遠慮をしていたり、「みんなも大変だから……」と隠れ我慢をしてしまっているようにも思います。

砂川:つい「わがままに思われないか」などと、周りを見たり、遠慮したりしがちですが、そうすることがかえって自分にも、周囲の女性たちにも良い結果に繋がらない場合もありますよね。そうした背景には「我慢が美徳」という考えを持つ人が、まだまだ多いからかもしれません。弊社にはロキソニンSという解熱鎮痛薬がありますが、2011年に、これまで病院でお医者さんから処方されていた医療用医薬品だけだったのが、自分で薬局やドラッグストアで、頭痛や生理痛等で痛い時に購入できる(スイッチOTCという)市販薬として初めて登場したんですね。
その当時「効き目の優れた解熱鎮痛薬が出たことで、より女性が生理痛などの痛みで悩む時間が減り、きっと多くの方のQOLに向上するだろう」と思ったのですが、アンケートをとると、「まだ、耐えられる痛みだから、我慢する」と言って、もう限界!となったら飲まれる方がとても多かったんです。
でも解熱鎮痛薬は、痛みが出たら早め早めのうちに飲んだ方が、体内で起こっている原因と対処のメカニズムの点からは正解なんです。我慢して痛みが増してから飲むと、それだけ和らげる事も大変になってしまう。速く痛みは取り、かつ、早くそもそもの原因があればしっかり病院で診てもらう。我々製薬会社がそのことをもっと発信していくことも大切ですが、そもそも痛みが出ても頑張れるところまで我慢する、という考えも変えていけたらいいですよね。
20代~50代の男女800名 日本人の「痛み」実態調査 ~頭痛やその対処法への認知率は低く、約7割が痛みを我慢~|第一三共ヘルスケア
周りと繋がることの大切さ
笹尾:チームで仕事をしているのに、自分だけ調子が悪いと言ったら申し訳ないとか思いがちです。でも調子が悪いままでいることこそ、チーム全体のパフォーマンス的にはよくないかもしれません。我慢はせず、チームだからこそ、それぞれ大変なときに補い合ったり、どうしていくべきか考え合ったりすることが大切なのではと思います。人は一人では生きていけませんから、周りに支えてもらったら、そのお返しをする――そうやって循環させていくことが、ウェルビーイングな社会に繋がっていきます。
砂川:自分一人だけで抱え込んでいたら限界もあるし、周りと繋がっていくことで解決することもありますもんね。
笹尾:繋がりはものすごく大切だと思っています。日本女性ウェルビーイング学会は、「繋がることで社会はもっと良くなる」をスローガンに、1人や1つの団体だけではできないことも、みんなが繋がり、情報発信することで、ウェルビーイングな社会になるよう活動しています。こうやって話すとつい難しく捉えてしまうかもしれませんが、ウェルビーイングは特別なことではないし、関係ない人は1人もいません。この世に生まれてきた以上、みんな幸せになる権利があるし、今よりももっとウェルビーイングな気持ちで仕事をして生きていくことは、男女関係なくみんなが持っている権利ですから。みなさんそれぞれ大変な思いをされていると思いますが、それを我慢するのではなく、①まずは自分のからだのことを知って、②どうしたら少しでも良くなるのか周りと話し合うことが大切です。自分たちが我慢してしまうと、結局下の世代まで我慢することになって、いつまで経っても日本の女性や日本社会全体のウェルビーイング度は上がっていきません。まず自分の身体のことを知って、自分がどういう人生を送りたいのか、それを考えることがまさにウェルビーイングの出発点です。

ヘルスリテラシーを上げるために情報を活用

笹尾:でも本当に、こうやって製薬会社がそれぞれのヘルスリテラシーが上がるような情報を発信してくれるのは、社会全体にとっても非常にプラスになりますよね。
砂川:ありがとうございます。第一三共ヘルスケアでは広報活動の一環として、「健康美塾」の他に、「くすりと健康の情報局」そして「ねこいちさん」と3つのメディアを運営していますが、その3つのメディアを使い分けて感じたのは、背景にどんな事情があるかが、情報を発信する上では大切だということ。「くすりと健康の情報局」では、ほとんどが検索で来てくれていますが、どこまで市販薬を使ってセルフケアができるかに加えて医療機関を受診すべき目安、薬の正しい使い方・管理・捨て方など、教科書的な情報を載せており、そこでは“寄り添う”ことよりも“今困っているこの症状や不調には何をすればいいか”が即座にわかることが一番重要になります。
一方、SNSや動画では、健康を気にかけようというアンテナが立っていない人たちに対して、まず生活習慣を見直してもらおうと、第一三共ヘルスケアのセルフケア啓発キャラクター「ねこいちさん」を使って発信しています。そこでは、栄養をしっかり摂ろう、規則正しく寝よう、お風呂はゆっくり入ろうなど、基本的だが大事なことを意外性のある切り口やテーマで届けることで、“気づき”と“今日からやってみよう”にテンポよくつなげられたらと思っています。
そして「健康美塾」では、生理や更年期をはじめ、女性特有の健康課題はみんなそれぞれ症状があって、正解は一つではないことを、寄り添いながら発信しています。
「健康美塾」は、他の2つのメディアに比べると、具体的な症状の対処法がすぐにわかる記事ばかりではないですが、日々生活する上でこの選択で合っていたのかな?より良く暮らすために必要な知恵がないかな?と悩める方に、寄り添って、道標になるようなサイトを目指しているので、色々な記事を読んでいただけたら嬉しいですね。
どのメディアも予防と受診勧奨がセットではありますが、情報をどんな人に、どのように届くと態度や行動の改善につながるのかを、重視して使い分けています。
笹尾:素晴らしいですね。働く女性も増えて、女性の声に耳を傾けるようになったからこそ、そうやって情報発信の仕方も変わってきたのは進歩ですよね。企業側がこうして変わっているからこそ、受け取り手である私たちがヘルスリテラシーを上げて、双方向のやり取りになっていくと、より良い未来になっていくのではと思います。
- 1
いいね!