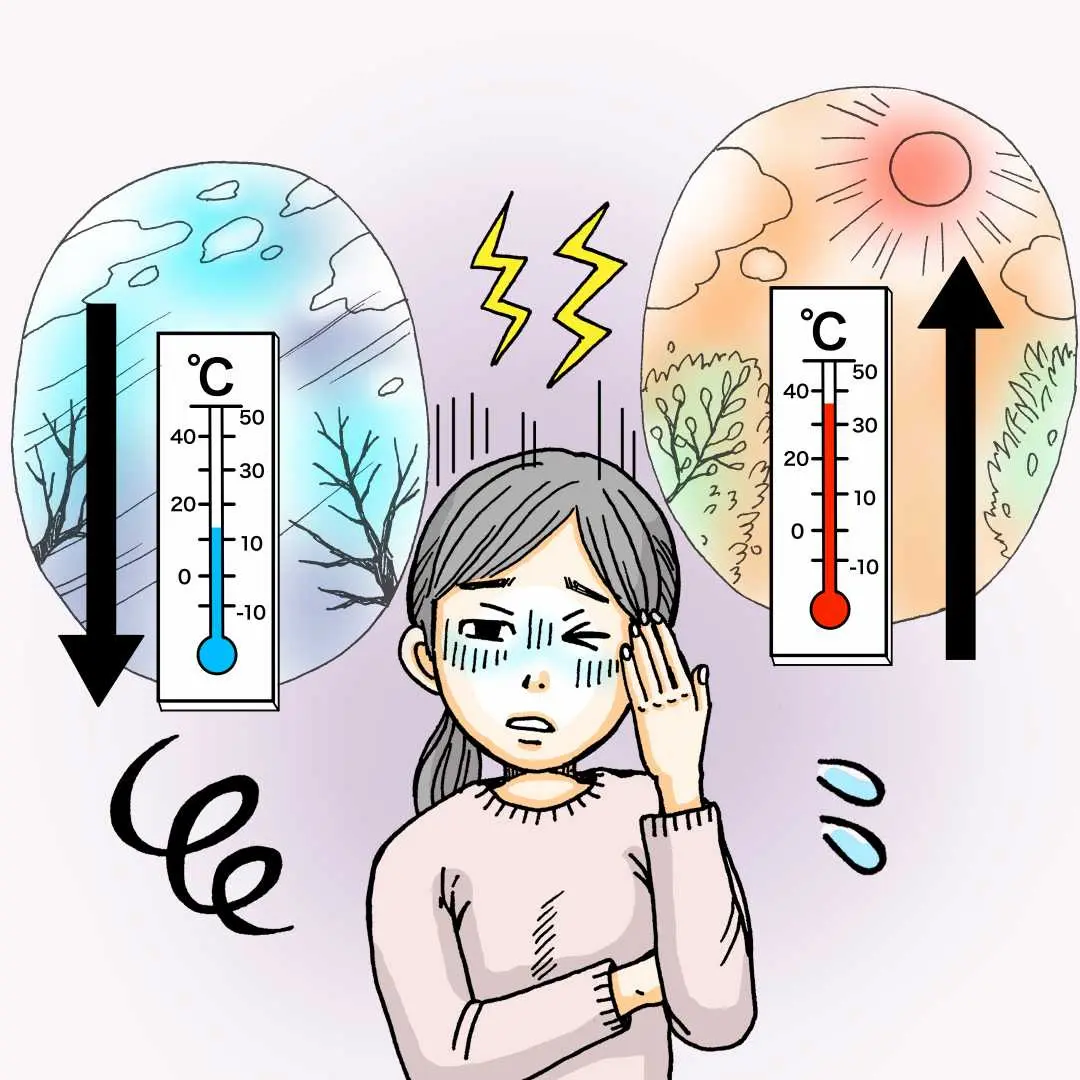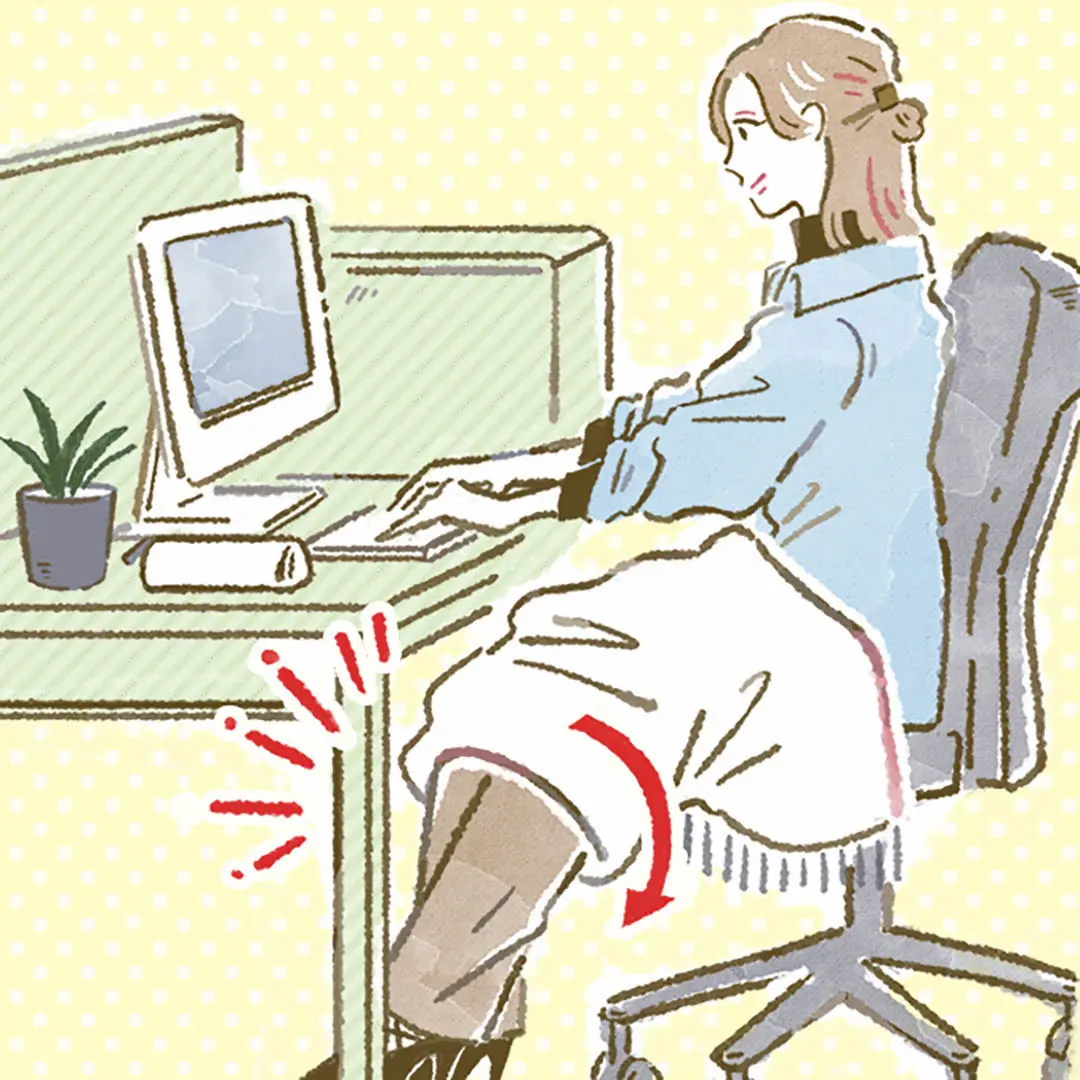「1日2Lの水」は飲みすぎ?からだに合った水分補給を見直そう

2025年07月01日
「水は1日2リットル摂りましょう」——そんなフレーズを、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
たしかに水分補給は人間のからだにとって欠かせないもの。ですが、体型や体重は人によって千差万別。それなのに一律2リットルでも良いものなのでしょうか?
水分の重要性や正しい水分補給の方法を、済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜先生にうかがいました。ついつい水分補給を忘れてしまうという方にもおすすめの“習慣化のコツ”も教えていただきます。
自分にぴったりの水分量ってどのくらい?
―雑誌やテレビなどで、最近「1日2リットルの水を飲むと良い」とよく聞きますが、これは誰にでも当てはまるのでしょうか?
谷口:いえ、誰にでも当てはまるとはいえません。本来1日約2リットルというのは食事に含まれる水分量も合わせたものなのですが、飲料の分だけを指して大体2リットルという言い方が広まってしまったのだと考えられます。
しかし、体格や日常の活動量、汗をかく量などは人それぞれなので、実際には1日2リットルの水分補給が適している人は全体の半分もいないのではないかと思います。
―では、自分に合った水分量はどうすればわかるのでしょうか?
谷口:万人に共通する考え方として“4-2-1ルール(医師が点滴の量を計画する際に使う計算式)”というものがあります。このルールでは、自分の体重をベースに、必要な水分量を次のように算出します。
たとえば体重が50kgの人の場合、以下のような計算になります。
【1時間に必要な水分量】
(1) 10kg×4=40ml
(2) 10kg×2=20ml
(3) 自分の体重(50kg)−20kg=30ml
(4) 40+20+30=90ml
【1日に必要な水分量】
90ml×24=2,160ml(2.16L)
体重別に1日の水分量目安をまとめると、以下のとおりです。

谷口:ただ、この数値はあくまで“食事で摂れる水分量”を含んだものなので、純粋に飲み物で摂る量は、およそこの半分くらいと考えると良いでしょう。
また上記の数値は、人が何もしないで安静にしている時に必要な水分量です。運動や力仕事をして汗をかいた場合には、計算によって求められた量に、失った汗の分を加えた量の水分を摂ることをおすすめします。
水分がもつ3つの重要な役割
―ところで、そもそも水分は、人間のからだにとってどんな役割を果たしているのでしょうか?
谷口:水分は、人間のからだのなかで大きく3つの働きをしています。
1つ目は、からだに必要なものを細胞に運び込む働き。血液などの水分は、私たちのからだを動かすために欠かせない酸素と栄養素を運んでいます。
2つ目は、代謝によって生じた老廃物を、尿や便というかたちで外に運び出すこと。
そして3つ目が、体温調節。代謝によって生まれた過剰なエネルギーを、汗を蒸発させる時の気化熱として放熱します。
普段の生活のなかであまり意識しないかもしれませんが、水分は生命活動を維持するために欠かせないものなのです。
また、病気の治療においても水分補給は最優先に行うものです。体内にきちんと水分量が保たれていないと薬が効かなかったり、手術ができなかったりといった悪影響も出てくるためです。

―水分補給を日常的に意識していないと、気づかないうちに脱水症になっている……なんてこともありそうです。脱水症状に気づくサインはありますか?
谷口:医学的には体重の2%以上の水分が失われたら脱水状態といわれています。自分で気づけるサインとしてまず挙げられるのは、集中力の低下です。脳に十分な酸素や栄養素が運ばれて来なくなると、ぼーっとしたり、立ちくらみが起こったり……。ひどくなると頭痛や痙攣、意識障害が起こることもあるんです。
また、筋肉に十分な水やミネラルが行き渡っていないと、力が入らなくなったり、こむら返り(筋肉が痙攣しつること)が起こったり、最終的には全くからだが動かなくなってしまうこともあります。さらに、胃腸に水分が行き渡らなくなると食欲が低下したり、下痢や便秘になったりといった症状も出ます。
それだけでなく、皮膚にも脱水の症状が現れることもあります。水分不足によって酸素や栄養素が行き渡らなくなると、老廃物が溜まって、色素沈着やハリの低下といった症状が出ます。実際に、脱水症状のある患者さんの皮膚を見ると、極度にシワが出ていたり、ツヤがなくなったりしているんです。そういったさまざまな症状が脱水によって引き起こされます。
水は足りなくても、摂りすぎても不調に。大切なのは“適量”
―脱水の症例をうかがうと、やはり「水はたくさん飲んだほうが良い」と思ってしまいましたが、水を摂りすぎるとからだに良くないこともあるのでしょうか?
谷口:そうですね。水を必要以上に摂りすぎると、からだに水分が溜まり、逆に不調を招くことがあります。
たとえば、水を飲み過ぎると皮膚がむくむのは何となくイメージできると思います。ですが実は、脳や心臓や肺などの臓器もむくんでしまう場合もあるんですね。脳がむくむと思考能力が低下したり頭痛や眠気に襲われたり、また肺や心臓がむくむことで命に関わる病気になってしまったりするのです。
短時間に多量の水だけを摂取することで起きる “水中毒(みずちゅうどく)”という病気があります。水分を摂りすぎることで、血液内の塩分濃度が薄まり、貧血のときのように意識が朦朧とする危険な病気です。これを発症すると、皮膚や臓器のむくみに加え、体重も右肩上がりに増加していきます。
「水をたくさん飲むと健康に良い」といった言説や、水ダイエットの流行などもありますが、水の摂りすぎには注意してくださいね。
―水分が少なすぎても多すぎても、からだには悪影響があるということですね。年齢によっても、適切な水分の摂り方は変わってくるのでしょうか?
谷口:基本的には変わりませんが、近年の研究では、40歳を過ぎた頃からは特に注意して、適切な水分量の摂取を心がけたほうが良いとされています。背景としては、水分量が不足すると老化が早まることに加え、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが高くなるからです。逆に、水分量が多すぎると、先ほど紹介したような臓器の病気など、40歳を過ぎて代謝や自己修復能力が落ちることでその症状が顕著に出やすくなることもあります。
そのため、自分の年齢や体格に合った水分量を把握しておくことが大切かと思います。

水分補給では、飲み物選びも重要
―ここからは適切な水分補給のポイントについて教えてください。まず、水分補給におすすめの飲み物はありますか?
谷口:基本的には水とノンカフェインのお茶がおすすめです。
まず、水は大きく分けて軟水と硬水があります。水を飲んでお腹が緩くなることがある人は、軟水を選ぶと良いでしょう。硬水に多く含まれるマグネシウムは下剤にも使われるくらいなので、体質的に合わない方はお腹を壊す場合もあります。
ただ、硬水にはミネラルも多く含まれているので、汗で失ったミネラルを補ってくれる効果もあります。慣れればからだに良い飲み物なので、挑戦してみるのも良いかもしれません。
また、胃腸の弱い方は冷たい水でなく、白湯のほうが良い場合もあります。人体に近い温度のほうが胃腸への負担は少ないですし、体温を下げずに水分補給できるので冷え性の方にも適しています。
また、炭酸水も水分補給にはおすすめです。炭酸が胃腸の働きを活発にして、水分を摂りやすい体内環境をつくってくれるんです。
―水分補給に飲むお茶の選び方にポイントはありますか?
谷口:また、お茶については、カフェインの有無に注意してください。お茶の成分に含まれているカフェインには利尿作用があり、飲み過ぎるとせっかく摂った水分も出ていってしまいます。また、日本人のなかには、カフェインを摂ると頭痛がしたり体調を崩したりする人もいます。そういった方は、緑茶よりもカフェイン量が少なめなほうじ茶や麦茶などがおすすめです。
コーヒーや紅茶にはカフェインが入っている場合が多いですが、飲み慣れていて利尿をもよおさない人であれば水分補給にはなります。ただもちろん、飲み過ぎはカフェインの摂りすぎにもなり、からだの負担になるので注意が必要です。
―逆に、水分補給に適さない飲み物はありますか?
谷口:基本的にアルコール飲料以外であれば水分補給になります。ただ、いまお話ししたカフェインに加えて、塩分と糖分が多い飲み物は、飲み過ぎると別の弊害を起こす可能性がありますので気をつけてください。たとえば、糖分が多いジュースを飲みすぎると、血糖値が上がりからだに負担がかかるので危険です。
24時間、からだに水分が行き渡った状態をつくるために
―日常のなかで、水分補給に適したタイミングを教えてください。
谷口:水分補給の目的は、からだに水分を維持させることなので、点滴のように24時間ゆっくりと水分を摂ることが理想的です。これに近い状態をつくるためには、つねに飲み物を持ち歩いて、こまめに水分補給すること。一度にたくさん飲み物を摂っても、からだのなかに水分がとどまってくれません。

特に起床時の水分補給は重要です。まずはコップ1杯の水を飲みましょう。寝ているときは水が飲めないので、体内から水分がかなり失われています。
ちなみに、起きてすぐの口内は口腔内が乾燥していて唾液も少ないために一番雑菌が多いので、少し口をゆすいでから水を飲むのがおすすめです。
―それでも、忙しくてつい水分補給を忘れてしまうこともあると思います。水分補給を習慣化するコツはありますか?
谷口:水分補給を習慣づけるために、“6オンス8回法”というのをおすすめします。6オンス(=180ml)の水を1日8回飲むという意味です。この水を飲む時間を、薬を飲むときと同じようにあらかじめ決めておくことをおすすめします。
たとえば、朝起きたとき、10時のおやつのとき、昼休みの時、毎回の食事のとき、お風呂の前後に1杯ずつ……とか。ライフスタイルに合わせて、8回のタイミングを固定しておけば、忘れずに水分を摂れるようになります。もっとこまめに管理したければ、チェックシートをつくってメモをしたりアラームをかけたりしても良いかもしれません。
体重や運動量、日々の体調に合わせて、回数は無理のない範囲で調整してみてくださいね。
水分は人間のパフォーマンスを維持するために、最も重要なもののひとつ。仕事で良い成果をあげたい、勉強で良い成績を取りたい、美容を頑張りたい……そんなあらゆるシーンにおいて、からだの基礎となる水分は重要です。
これらを維持したい人は、ぜひ水分補給を習慣に取り入れてみてくださいね。
- 1
いいね!